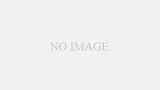移住と一口に言っても、山あり谷あり様々な経験をするのは当然のことです。あっという間に月日は経ちましたが、石の上にも3年、昔の人は良く言い当てたものだなあと思います。
まったく見知らぬ土地へ、知ってる人もおらず身寄りもなく、単身よくぞ奄美へ飛び込んだものだと、今更ながら自らの無謀さに気がついています。私の場合移住した理由は「暖かいから」といつも答えているのですが、それだけの理由で?と島の人に怪訝な顔をされます。しかしその通りなので、他の言い方はありません。
私が住む場所は、中心街の名瀬から北へ行って、奄美空港も越えた1時間くらいかかる最北端の田舎の集落です。田舎生活をしたいから此処を選んだという理由ではなく、島で住居探しをした結果、借りられる物件がこの集落にしか無かったと言うのが真の理由です。集落によって言葉や文化、人柄や性格が違うとかいう後で知る大事な情報は全く研究していなかったのです。行き当たりバッタリ、借りれれば何処でも良いという感じでした。
結果的にではありましたが、私が住むことになったこの集落は八月踊りの伝統行事が今も深く根付いている、奄美の中でも最も奄美らしい地域らしかったのです。(また古い時代の奄美が、最初に海洋交流を開いた玄関口でもありました)しかし同時にパンデミックの最中に移住したものですから、それらの行事が全て中止、私は仕事は学校関係に週3日通うものでしたが、地域の伝統行事は全て中止で参加することはできませんでした。残念でしたが、行事を通じて集落の人たちと黒糖焼酎を酌み交わしながら自然に溶け込むというチャンスを、3年間逸してしまったことは不運だったと思います。
沖縄移住した人たちのグループを主催する人が言っていた言葉がとても印象的です、「移住には3つの壁がある。1つ目は住居の壁、2つ目が仕事の壁、3つ目が孤立の壁だ」と。これはごくごく最近知った言葉でしたけれど、移住について誰もが考えなければいけない重要な課題を端的に言い当てています。
どれも大変重要な指摘なのですが、1番のポイントは「孤立の壁」と言っていました。まさに最重要な課題であると同時に、この課題を乗り越えられず移住から撤退する人は実に多いのだと考えています。これは移住に限りませんよね。都会に住んでいても実は同じです。しかし田舎の孤立は辛く、孤立ほど大きな支障はありません。沖縄のグループは、移住者同士が横で繋がりサポートし合うという関係づくりをしているようです。奄美ではそういった取り組みをしている活動はないです。
私にとっても、「孤立の壁」は大変大きい課題であったと思っています。まして基本「独居」ですので、精神的安定のためにも島人(しまんちゅ)との触れ合いは重要です。「一人でノンビリ、海で泳ぎ、南国トロピカルフルーツでも嗜んで、優雅な生活を」といきたいところですが、そうは簡単ではありません。生活と経済はついて回るものですから。
私の場合、その「孤立の壁」はグランド・ゴルフを始めたことがとてもいい方向へ突破口を開いたという感じがしています。しかしそのことに気が付くのに「石の上にも三年」は実に適切な言葉だったと感じています。次回も「石の上にも3年」について書いてみたいと思います。