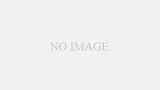「三日踊って三日休み三日踊る」大笠利の八月踊りは日本最南端の離島に残る天下の「奇祭」だ。奄美の伝統文化でどこの集落(しま)でも盛んに行われていたが、年々縮少されて数年後に消滅するのではと囁かれている。実際昔の3日3日3日ルールを守っている集落は少なく「八月踊り」自体やめた地域もある。今まさに伝統文化存続の瀬戸際だ、心ある人達はそれを「残そう」と必死だ。大笠利は最も奄美らしい「八月踊り」がそのまま見ることができる。
9月の末に行うのになぜ「八月踊」と言うのか不思議だったが、旧暦8月「豊年祭」の意義を込めて踊る祭りだと分かった。島の南部の方は「踊り」の形式よりか神事としての「奉納相撲」をメインにして行なっている地域が多く、地域によって形式は微妙に違っている。
コロナの最中の4年前に移住したので実は「八月踊り」は4年間中止だった。だからこの祭りの「凄さ」「奇抜さ」「底知れぬパワー」を知らないで過ごしたことは痛恨の極みだった。「八月踊り」を知らずして「奄美」を語ること勿れ。もしコロナが無くて、移住早々に「八月踊り」に参加したら私は一気に集落(しま)に溶け込んでいただろう。八月踊りには一瞬で人々を融合してしまうパワーがある。観光で見えない「本質的な何か」を人々が見せてくれる「生の奄美」「本音の奄美」の世界だ。男女が恋の駆け引きの歌などを掛け合い、焼酎を回し飲みして深夜まで踊り狂う。(パンデミック以降回し飲みはなくなった)
北部集落でも村ごとに踊り方やリズムや歌詞が違うのは不思議である。隣の集落であっても違う。プライドなのか集落独自の歴史か。薩摩藩は隣村の人との結婚を禁じたと言う。交流がなかったからこそ「八月踊り」は数百年間かけて独特な「八月踊」の宇宙を構築した。(続く)