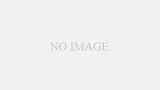奄美へ来てすぐに「三線」を習い始めました。「三線」は奄美の魂を表現する重要な楽器です。
「異文化交流勉強会」というのをバレー部OBK先輩主催で毎月川越でやっています。内容はかなり高度なテーマが多く大学の教授や、地域の研究家や気鋭の NPO法人の代表を招いての勉強会です。勉強自体は最長40分くらい、後は食事とお酒を嗜む交流会がメインのフラットな会です。まあ飲み会ですね。
私は、既に奄美移住から2年でしたが、そのK先輩から電話で「奄美へ移住して」という題で話をして欲しいとの依頼がありました。少しの躊躇はありましたが半分は嬉しい気持ちもありました。無謀な単身奄美移住もいくらか評価する人がいるのかも。「短時間でいいし、主題は他の人がやるから副主題で気軽に」とのことで引き受けることにしました。日程も私に合わせると。三味線もかなり練習していたので寧ろそれを披露したいという考えの方が強かったです。
簡単な原稿を準備しました。古民家を改造した「民泊」が会場でした。話して感じたことは、「環境を変えてみる」「身の置き所を変えてみる」ことの意味です。「異文化交流勉強会」が「比較文化論」だったので正に私の話はジャストミートで「奄美」と「川越」の「比較文化論」になり質問は多く、「移住」というテーマに多くの人が関心を持っているのだなあと思いました。
15分くらい「奄美」の移住話をして、あとは10分くらいは「行きゅんやかな」と「糸繰節」を演奏しました。酔が回って川越の古民家で弾く三線の音にうっとりして川越の夜は更けていきました。遠方から来た私への労いで皆さん300円ずつ寄付をくださり、私の食事代はただになってしまいました。
なんかいいことをしたような気持ちになりました。