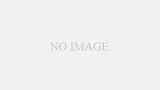「八月踊り」奄美の最大の風物詩。鹿児島市、大阪東京の子息親戚が懐かしい踊りに参加するため故郷へ一斉に帰ってくる。毎年「八月踊り」のためだけにやってくる「八月踊りファン」も都会から田舎に帰ってくる隠れ島人(しまんちゅ)も多い。関西が多い気がします。昨年は特に4年ぶりに行われたものだから、その「ファン」の数が多くて半分位が島外の人達だった感じがします。限界集落のようなこの村もこの時ばかりは若い人たちが大勢集まってきて賑やかです。
「八月踊り」は「豊年祭」であるとともに場所により「種おろし」とも重なる。新暦9月末 農産物豊作を神に感謝する。最初の3日間を「アラセツ」そして3日間休みまた「シバサシ」を3日間踊る。初日の公民館を出発して夕方7時半から9時半まで各家庭を3場所「家まわり」(やまわり)する。その家の繁栄と家内安全そして勢いよくみんなで踊り悪魔災厄追い払う意味がある。
一場所終わるり次へ行く際は男が「追い声」を上げ「女のちぢん」(太鼓)で次の場所へ移動する。「家まわり」はとても風情があるものだが食事のもてなしを準備する家庭とその班はすごく忙しい。家ごと腕によりをかけたご馳走を用意し黒糖酒、ビールが振る舞われる。踊りながら焼酎の回し飲みが行われる(コロナ以降自粛)。子供達はこの日沢山のお菓子、ご馳走をもらって大きな袋に詰め込む。大人たちは焼酎を煽って陶然として踊り舞う。八月踊は太鼓と三味線に合わせ円になって男と女が歌を掛け合うのが特徴である。歌詞は割と男女の恋の駆け引きの歌が多いような気がする。あと農業の知恵や生活の知恵を伝えるような歌も多い。最初はゆっくりしたリズムから始まって徐々に早くなっていく。最後は「六調」を舞い踊り狂うのだ。
三味線とちぢんの音が真っ黒な世界に吸い込まれていき、酔意はさらに回って恍惚としたトランス状態の様な不思議な世界に没入する。それは言葉で言い尽くすことができない。設置された淡い手作りの白熱灯の淡い光が独特なムードに島人(シマンチュ)を誘う。
読んでくださりありがとうございます。